�@�@�@�@�@ 
�@���ю��̊T�v�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �쉀�R�@���@�� ��
�E�R���G�@�쉀�R(��傤����)
�E�@�h�G�@�^���@�������h
�E�{���G�@�q�������n����F
�E�n���N�G(�`)�a��5�N(712�N)
�E�J��;�@(�`)�m�E��d(���傤��)
�E������;�@�\��ʊω���F����(����)�A
�@�@�@�@�@�@�@ �Α��n����F���� etc
|
�@�`���ł͘a��5�N(712�N)�ɑ��������y��
(���݂̒k�R�_��)�̕ʉ@�Ƃ��ē���������
���q�E��d(���傤��)���n�������Ƃ����B
�@���ю��̋ߐ��܂ł̗��j�͕s���̕���������
��,�]�ˎ���ɂ͐������S(���傤��傤����)
���O�֎R�������̕ՏƉ@���ڂ��čċ������Ƃ����B
�@�]�˒����ɂ͕��t����(�Ԃキ�Ă�����)�ɂ�茻�݂̖{���E�q�������n����F����
���u���ꂽ�B
�����̐_�������߂̍ۂ�,�O�֖��_(��_�_��)�_�{���̑��֎�
(���������, �����݂�ł�)�{���̏\��ʊω��������ю��Ɉڂ��ꂽ�B
�@<�Q�l����>�@ Wikipedia�G�u���ю��v
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�A �p���t���b�g�G�u�쉀�R ���ю��v
�@�@�n�������̉����͏Ď��B
�@����,�����ɂ͎R��,���ʂɖ{��,���̍���Ɋω���������B
|
�@
�@JR����w����R�~���j�e�B�o�X�ɏ��, 8�����Ńo�X��u���ю��O�v�ɒ����܂����B
�o�X�₩��R�ۂ�]�ނƂ���炵�������������܂��B
�@�o�X��O�́u���ю��v�̊Ŕɏ]����, �����ȏW���̂���⓹�������, 5�����Ő��ю��ɒ���
�܂����B
�����, �܂�ŏ�ǂ̂悤�ȐΊ_�̏�̍���ɘȂ�ł��܂��B
�@�����ȎR��ł��B
�R��̉E��ɂ́u��E�O���v�ƍ��܂ꂽ�Δ肪�}���Ă���܂��B
���́u��E�O���v�Ƃ�, ���Ȃ鋫���Ƒ��E�Ƃ��鋫�E���Ӗ����܂��B
�َ�, �s��҂ł��������Ȃ�����Ă��炢�܂��B
�@�R���������Ə����Ȓ������őΖʂɖ{��������܂��B
�����̎R���ł���u�쉀�R�v�̝G�z�������Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N����Ƒ��ʂł����ɂȂ�܂�(�ȉ����l)

���ю��@�{�� |
|

�u�쉀�R�v�̝G�z |
|
�@�q�ϗ�400�~���Ė{���ɓ���܂����B
�����ɖ{���̑傫�ȐΑ��̒n����F���������u����Ă��܂��B
�{���̘e���Ƃ��č��E��,�u���P���q�v�Ɓu�������q�v�̃R���r���B
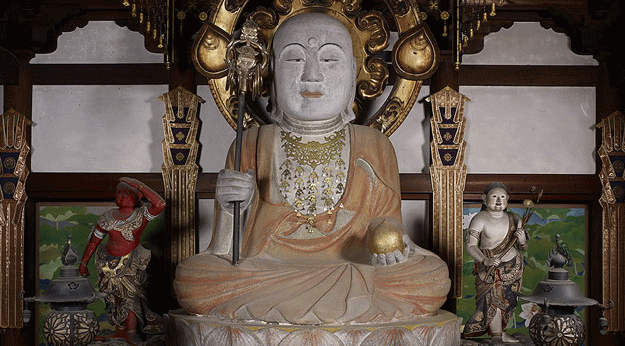
�n����F����(�q�������n������)�@<���ю���HP���]��> |
�@�����낢(����)��h�����悤�Ȕ����傫�Ȃ���ł��ˁB
���܂�̑傫���ɂт����肵�܂����B
���Y�Ǝq�����̂��n������Ƃ��Đl�X�ɐe���܂�Ă����Ƃ̂��Ƃł��B
�@���̒n����F�̉E�ׂɂ�,�~�q������܂��B
����20�N,�č��l�E�A�|�l�X�g�E�t�F�m���T�Ɖ��q�V�S�����F�R���Ē����ɖK��,�{���E�\���
�ω��������Č��܂����Ƃ����B
���̐~�q��, ���̌�,�t�F�m���T���ω�����̂��߂Ɋ�i���ꂽ���̂������ł��B
�~�q�ɂ͎ԗւƃ��|�����t�����,�L���̍ۂ̔�펝���o���̍H�v������Ă��܂��B
���݂�, �S�،��z�̊ω���(��ߓa)�ŕۑ�����Ă��܂��B
�@�{������L���`���ɊO�֏o��Ɗω����ւȂ���K�i�̓n��L��������܂��B
�K�i���オ���������E��Ɋω���������܂����B

�ω����ւ̓n��L�� |
|

�ω���(��ߓa) |
|
�@���悢��, ����E�\��ʊω���F�����ɂ��ڂɂ�����܂��B
�g�̏�̑傫���ω������, �K���X�P�|�X�Ɏ���Ē������Ă��܂����B
���グ�Ȃ���, ��������q�ςł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���c�N����Ƒ��ʂł����ɂȂ�܂�
�@�E�V������(8���I)
�@�E����; 209.1 cm
�@�E���w; 260.6 cm
�@�@�@�@ (����,�ޗǍ���������
�@�@�@�@�@�Ɋ����)
�@�E����@ 77.8 cm
�@�E�ؐS������
�@�@��܂��Ȗؒ����̌��^�����A����
�@�@ ���^�Ɏ��Ɩ؛���(���������邵)��
�@�@�グ�čו����`���A��������������
�@�@�Z�@�B
�@�ϐ��̂Ƃꂽ��, �L���Ȋ痧��, �ʊ��̂���㔼�g, �������Z�߂�����Ȏw��B
�~���̃��B�[�i�X�Ɣ�r����鏊�Ȃł��傤���B
��������E���ɗ������(���傤�͂�), 2�i�ƂȂ��Ă���V��(�Ă��)�B
�D���ł��ˁB
�@�w��≡��͏����I�ł���, ���ʂ��璭�߂��\��͒j���I�ł��B
�������������悤�ɐَ҂Ɏ����𓊂������܂��B
�@�\��ʊω������, ����������Ɋ�������ċ~�����{���Ƃ����B
��, �ω��������Ă����Ƃ����������v��,�a���瓦��, ���Y,�ߕ�,���H�͖�������,�Q����
�M�a�ɖ`���ꂸ, �l���瓁���ŊQ���ꂸ, ����Γ���Ȃ�, ��Ƃ̎��𐋂��Ȃ�,etc �Ƃ̂��ƁB
�����̌������{���Ă��炦���, �َ҂��S����B�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��ˁB
�Ɖ]�����Ƃ�, �P�Ȃ�Ô��p�ӏ܂����łȂ�, �����ƍ����ɔM�����߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��������
����B
�����B
�t�H�g�G�@2013�N4��17��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  TOP�y�|�W�֖߂� TOP�y�|�W�֖߂�
|
|