�@ �@�@�@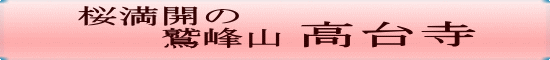
�@�@�@1)�q�@�ρ@���G2011.04.11(��)
�@�@�@2)���@�݁@�n�G ���s�s���R�捂�䎛���͌���526�Ԓn
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(JR���s�w���s�o�X���R����o�X�≺�ԁE���֓k��5��)
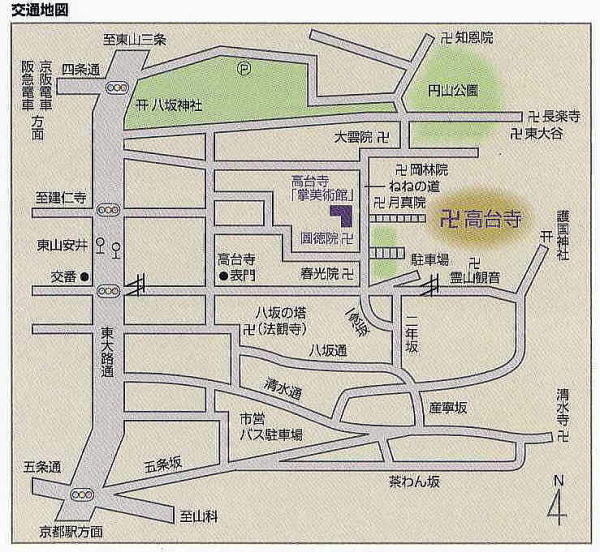
���䎛�ւ̌�ʒn�}
���p���t���b�g�u���䎛�v��聄
|
�@�@�@3)�V�@�@�@��G �ԓ܂�A18��
�@�@ Diary / No.355�|2011.04.12 /�u���s�E���R�Ŗ��J�̍������ł�v Diary / No.355�|2011.04.12 /�u���s�E���R�Ŗ��J�̍������ł�v
|
�@���䎛�̊T�v�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h��R ���䎛
�E�R���G�@�@ �h��R
�E�������G�@�h��R�@��������T��
�E�@�h�G�@�ՍϏ@���m���h
�E�{���G�@�߉ޔ@��
�E�n���N�G�@1,606�N(�c��11�N)
�E�J��G�@����@(�k����)
�@�@�@�@(�L�b�G�g�����E�˂�)
�E�ʏ́G�@���G�̎�
�E�������G �쉮,�J�R��,�ό���
�@�@�@�@�@���{���F�L�b�G�g��,
�@�@�@�@�@�L�b�G�g�����ق�(�d�v������)
|
�@�c��3 �N(1,598�N)�L�b�G�g�a�f��C�G�g�̐���
�ł���k�����i�˂ˁA�o�ƌ�͍���@�Ό���j���G�g
�̕������߂̎��@�̌����肵�C���̌���
�ҁE����ƍN�̎���������������Čc��11�N
(1,606�N)�ɊJ�R���ꂽ�B
�����͑����@�̎��@�ł������B
�@���i���N7���i1,624�N),���䎛�͗ՍϏ@���@��
���錚�m���̎O�]�Љv�𒆋��J�R�ɏ��فB
���̎��A���䎛�͑����@����ՍϏ@�ɉ��@���Ă���B
�@���̌�A�ߐ���������ߑ�Ɏ��鐔�x�̉Ђŕ��a�A����Ȃǂ��Ď��B
�n�����̌������Ō������Ă���̂́A�O�]�Љv���J��J�R���A�G�g�Ɩk�������J��
�쉮�i�����܂�j�A�����̎P���Ǝ��J��,�\��C�ό���Ȃǂł���B
�|�|�ȏ�CWikipedia ���甲���B�|�|
�@
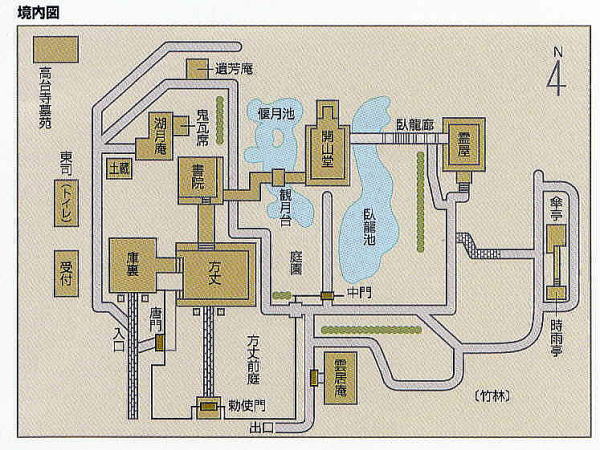 |
���䎛�̉����z�u
<�p���t���b�g�u���䎛�v���>
|
�@�@ �@ �@�@�Q�l�G �@Wikipedia�G�u���䎛�v
�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�A�p���t���b�g; �u���䎛 �R�� �h��R�v
�@�@�@�@ ���䎛�z�|���y�|�W�Ghttp://www.kodaiji.com/ ���䎛�z�|���y�|�W�Ghttp://www.kodaiji.com/
|
�@
�@�˂˂̓����璷���ɂ₩�ȐΏ�̑䏊�������ė���ƍ��ɒ����܂��B
����́C�����̏�����̂悤�Ȃ��̂ł��B

�Ώ�̑䏊��ƍ��䎛�̍�� |
�@����������ƍ���ɑT�����L�̌ɗ�������܂��B
���̉������̔q�ό����狫���֓���܂����B

���䎛�E�ɗ� |
�@�q�Ϗ��H�ɏ]���Đi�ނƕ���,���@�̔w��ɓc�ɉ����̈�F���ƌ�������������܂��B
�Lj�t�ɐ݂���ꂽ�~��������ł��l�B

���䎛�E��F��(�����ł�) |
�@�����ĕ���̓����ɓ���܂����B
�吳���N(1912�N)�̍Č��B�n�������̕���͕��\�̖�(��1)��ɕ�����̌������ڒz����
���̂����������ł��B
�O��Ɍ͎R�����L����}����������J�ł����B
�@(��1 )���\���N(1,592�N)�C�L�b�G�g�����̐�����ړI�ɗ������N�ɏo�������N���푈�B
�@�@�@�@��16 ���̌R�����R�ɏ㗤�������̍����܂Ői�o�������A���̉��R�A���N���R�̍U���▯�O�I�N�Ȃǂɂ����
�@ �@�@ �ƂȂ藂�N(1,593�N)���B

���䎛�E����O��C���g��Ɩ��J�̎}����� |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N����Ƒ��ʂł����ɂȂ�܂�
|
|
|
|
|
|
| ���䎛�E����O��̖��J�̎}����� |
�@������o�ĎQ��������ƒ뉀���L����J�R������]�ł��܂��B
���@�ƊJ�R�������ԉ����t���̘L���̓r���Ɋό��䂪�����܂��B
��������k�����͖S���G�g�����̂тȂ��猎�߂��Ƃ����B
�O�畘�̎l�{���̌����ŁC�O���ɓ��j�������������������Ă��܂��B

���䎛�E�ό���ƊJ�R�� |
����(�d�֖�)��������Ɛ���(���@�̓���)�ɊJ�R��,�E��͉痴�r(����イ��)�ł��B

���䎛�E����(�d�֖�) |
�@�J�R����,�c��10 �N�i1605 �N�j���z�̓��ꉮ���E�{�������̑T�@�l�̕����B
�����A�k�����̎��������������̂ŁA���̌�A�����J�R�̎O�]�Љv�̖ؑ����J�铰�ƂȂ��Ă���B
�@�����͒������ɎO�]�Љv���A�������ĉE�ɖk�����̌Z�̖؉��ƒ�Ƃ��̍ȁE�_�Ɖ@�̑��A����
���䎛�̕����ɐs�͂����x�����̖ؑ������u���Ă���B
���̓��̓V��́A�G�g�̌���M�̓V��ƁA�k�����̌䏊�Ԃ̓V���p�������̂Ƃ̂��Ƃł��B

�J�R���̐��� |
 |

�@(��)�J�R���Ɖ痴�r
�@(��)�痴�L
�@�@�@�J�R���́C�����t���̊K�i�ŗ쉮
�@�@�@ (�����܂�)�ƌ���Ă��܂��B
�@�@���̔w�Ɏ��Ă���Ƃ��납��痴�L
�@�@ �@�Ɩ��t�����Ă��܂��B
|
�@�쉮(�����܂�)�́C�c��10�N(1605 �N)�J�R���̓����̈�i�����Ȃ����~�n�Ɍ����A��`��
�w�畘���̓��ł��B
�k�����̕揊�ŁA�G�g�Ɩk���������J�肵�Ă���B
�~�q�����E�ɂ͏G�g�Ɩk�����̖ؑ������u���Ă���܂��B

���䎛�E�쉮(�����܂�) |
�@�쉮���o�ċ��������̏������u�ɏオ��Ɓu�P���v�ƌ�������������܂��B

�����E�P�� |

�P���̓����̓V��ł� |
�@�@�����邩��ڒz�������̂Ƃ���A�痘�x�̍�ŏG�g�D�݂̒����Ɠ`�����Ă���B
�@��`���������̑f�p�Ȍ����ŁA�����̓V�䂪�|�ŕ��ˏ�ɑg�܂�A���̌`�����P��
�@���Ă��鏊����P���̖�������܂��B |
�@�@�P���̓�ׂɂ͎��J��(�d��)�ƌ�����K���Ă̒���������܂������C�C���H�����ł����B
�P�����l�����邩��̈ڒz�Ƃ���A�痘�x�̍�ŏG�g�D�݂Ɠ`������B
�@�|�т̍ד���ʂ�q�Ϗo������o��ƒ��g�傪����܂��B

���䎛�E���g�� |
�@�吳���N(1912 �N)�ɕ���ƂƂ��ɍČ����ꂽ���̂�,����̓쐳�ʂɂ���܂��B
�䏊��̓쑤�ɏ��O������܂��B

���䎛�E���O(������2010�N�ɐV�����t���ւ���ꂽ) |
�@�d���̞���(����;2 m, ���a; 1.1 m, �d��; 2 ton, 1,606 �N����, �؉��ƒ�̊�i�Ƃ����)
�́C�V�����̂��ߖ�400 �U��ɐV����(�ʐ^)�����ɕt���ւ���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B
�@���䎛�̔q�ς��I���đ䏊�������C�u�˂˂̓��v�̌������ɂ��隢���@��q�ς��܂����B
���䎛�̓����̈�ŁC�G�g�̐����E�k����(�˂ˁC����@)���ӔN���߂��������Ƃ��Ēm����
���܂��B
�؉��Ƃ̕�Ƃ��ĊJ���ꂽ���̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�ɂ���
�E�@�h�G�@�ՍϏ@���m���h
�E�{���G�@�߉ޔ@��
�E�n���N�G�@1,605�N(�c��10�N)
�E�J��G�@�O�]�a��
�E�������G �뉀(���̖���)
�@�@�@�@�@���J�쓙����u�~�̊G�v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�d�v������)
|
�@����@�̉��ɓ�����؉����[���A������̉���
�a������̓@�Ɉڂ��Ď��Ƃ����̂Ɏn�܂�B
�����̚����@�͗��[�̖@������Ƃ�ꂽ���̂�
����B�Ȃ��A���̎��Ɉ��u����Ă���O�ʑ单�V��
�G�g�̔O�����Ƃ����B
�@������C����C����C�����C�k���@�C�k��C��납��Ȃ�B
�@
�@ �@�Q�l�G �@Wikipedia�G�u�����@�v
�@�@�@�@�@�@ �@�A�p���t���b�g�G�u�����@�v�@
|
�@�������������ƑO���ɓ��傪����Ώ�ŕ���ւƑ����Ă��܂��B

�����@�E������ |

�����@�E���� |
�@(��)������G�ߐ����喼�̕��Ɖ��~��Ƃ��Ĕ��������`���B
�@�@�@���喼�́A�����̉��~�̎��͂ɁA�Ɛb�Ȃǂ̂��߂̒��������ďZ�܂킹�Ă������A���̈ꕔ�ɖ���J���āA
�@�@�@��Ƃ�������������̎n�܂�ł���B

�G�g���D�݂̎萅�� |

�����@�E���� |
�@����ɂ͒��J�쓙����̉��G�u�~�̊G�v(�����C�d��)������܂����C�˖���U�炵�������ɕ`��
�ꂽ���G�Ŕ��ɒ����������ł��B
�������Z�E�̗��璆�ɏ���ɕ`���Ă��܂����Ƃ����G�s�\�|�h�������i�������ł��B
���͑哿�������O���@�̕���������Ă���36 �ʂ̓�32 �ʂ��C�p���ʎ߂ɂ���Ă����Ɉڂ���
���̂ł���B
�ܘ_�C���J����Ă������͕̂ۑ������l�����Ă��̐����ȕ����ł����B
�߂ނȂ��ł��l�B
�@����̑O�낪���ł��B

�����@�E���͎̌R�� |
�@���䂩��n��L����i�ނƖk���@������C���̑O�낪�k��ł��B

�����@�E�k���@ |
�@�k��͂��Ƃ��ƕ�����k�������ό�a�̑O����ڂ������̂ŁC�����̌��^���قڂ��̂܂܂�
���߂铍�R����̑�\�I�뉀�̂ЂƂł��B

�����@�E�k�� |
�@�����Ō�ɏ��x���B������������r���V���͎̌R���ł��B
���̒뉀�́C�����̂悤�ɑ�R�̐��z�u���ꉽ�ƂȂ������Ȋ��������܂��ˁB
�����ɂ��ƁC�����̐́C�G�g�����喼�ɖ����Ċe�n����W�߂����Ƃ̂��Ƃł��B
�@�Ō�ɋ߂��̍��䎛�u�����p�فv�ɓ���܂����B
�����́C���䎛�Ɗ֘A�e���@�Ɏ�������Ă������i�𒆐S�ɍ���@�䂩��̕i�X��W�����J
����{�݂ł����B
�����̏d�v�������̎��G�̒��x�i���W������Ă��܂����B
�@���̌�C�܂����Ԃ�����܂����̂ʼn~�R��������m���@������č������\���Ă��܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ TOP�y�|�W�֖߂� TOP�y�|�W�֖߂�
|
|